こんにちは、帯広は先日も大雪による臨時休校…大変でしたね。
なぜ春にこんなまとまった雪が降ってくるのか
もうすぐ外スポーツはシーズンインだというのに
雪に埋まっている物置からなかなか自転車が取り出せないでいる。あと2週間ほどで長男は競技場までのチャリの往復が始まるのに未だ積もりゆく雪…悲しい。笑
さて、そんなことはさておき、臨時休校になったら困ること…いろいろありますよね。
大人と子供それぞれにとって異なる困りごとを引き起こす可能性がありますね。大人目線と子供目線それぞれの困りごとを挙げてみます。
大人目線での困りごと
- 仕事との両立
子供が家にいるため、在宅勤務中の集中が難しくなることがあります。特に小さなお子さんがいる家庭では、親の注意が分散されがちです。 - 預け先の確保
共働き家庭などでは、臨時の託児所や親戚に頼る必要が出てくる場合があります。 - 計画変更の対応
臨時休校により予定していた仕事や予定が変更を迫られることがあり、ストレスにつながる可能性があります。 - 交通機関の影響
大雪自体で通勤が困難になるケースも多く、物理的な移動の制約が追加されます。
在宅ワークで普段家にいない時間帯に子供たちがいるのは大打撃ですね。中学生以上になってくるとどうとでもなりそうですが、小学生や 未就学児の場合は話を聞いてくれても予期せぬことが起こりがち…笑
また、出勤するタイプのお仕事の場合は子供をどこに預けるか、通勤はいつも通りにできるのか、など頭を悩ませる問題がたくさん。
先ほどの大人目線の困りごと4つはAIさんからお話を聞いたものですが、この中に入っていない最も重要な案件が一つあります!
それは、急遽必要になった子供のお昼ご飯です!
忘れてはいけない食事の用意
毎日朝晩のご飯を作るだけでも大変なのに、昼ごはんまで!
食材があれば難なくクリアですが、買い物直前で冷蔵庫に何もない!
て時は最悪ですね;
ですが、大人は何としてでも解決して仕事をしますよね
逆に子供たちが臨時休校で困ることとは?
子供目線での困りごと
- 学習の遅れ
学校に行けないことで授業が進まず、特に受験生などには大きな不安が生じることがあります。 - 運動不足
雪が積もることで外で遊ぶことが難しくなり、運動不足になりがちです。 - 友達との交流不足
学校が休みだと友達と会えず、孤独感を感じる子もいます。 - 退屈感
特に家の中でやることが限られている場合、時間を持て余す子供もいるでしょう。
体を動かせない!友達と会えない!面白くない!
簡単に言うとこんなところですね。なんともかわいい悩みですが子供にとっては一大事!
しかし、親として一番気になるのは「勉強の遅れ」だと思います。
一日中子供につきっきりにもなれないし、どうしたものかと頭を悩ませるはず。
そこで、今度は子供がお家で集中して勉強する方法を調べてみました。
1. 子供の集中力を高める学習環境の作り方
具体的にどんな方法があるのか確認してみましょう。
勉強に集中できる静かな場所を選ぶ
家の中のどこがベストなのか、テレビやゲーム、おもちゃがある部屋ではなかなか気が散って集中できないですよね。自分が集中したくても周りの人が騒いでいたりすると、落ち着かなかったりしますよね。周りからの協力も必要だったり。
整理整頓の重要性
物を減らす「断捨離」方法や、文房具をきれいに収納するアイデア。勉強するのにまずは机の整頓から…ありがちですが、ちゃんとキレイにしてから勉強をスタートした方がはかどりやすい。
照明と温度の調整
LEDライトや自然光を上手に活用する。約500~750ルクスが勉強しやすい明るさだそうです。わかりやすくいうと500ルクスは 曇りの日の窓辺くらいの明るさ。文字を読むのに十分な明るさですが、少し控えめな感じです。750ルクスは明るいオフィスや教室の平均的な照明の明るさ。このくらいだと、本や書類がはっきり見やすくなり、目が楽です。
2. 学習リズムを作る時間管理のコツ
時間割作成のメリット
家庭用ホワイトボードやアプリを使った簡単な時間割作成の方法。年齢にもよりますが主体性にまかせ時間を決めないでいると、いつまでも始まらないし、終わらない事態に。
休憩の質を高める工夫
深呼吸やストレッチ、瞑想、ヨガ、観察、ジャーナリングなどの簡単なマインドフルネス活動でリフレッシュする。大人向けな感じがしますね。子供向けにわかりやすくなったものはこちら。
1. 風船呼吸
- 子供に「お腹が風船だと思って、大きく膨らませてみて」と伝えます。息を吸うときにお腹が膨らみ、吐くときにゆっくりとしぼむイメージを持たせましょう。
- 呼吸を意識させるシンプルな方法で、楽しいと感じてもらえることが多いです。
2. 五感ゲーム
- 「周りで見えるものを5つ、聞こえる音を4つ、触れる感覚を3つ、香りを2つ、味を1つ見つけてみよう!」というアクティビティです。
- 子供が周りの世界に注意を向け、現在の瞬間に集中できるようになります。
3. おもちゃ観察
- お気に入りのおもちゃをじっくり観察する時間を作ります。「何色かな?どんな形かな?触った感じはどう?」と質問をしてみましょう。
- 子供に集中力と観察力を養わせるのに役立ちます。
4. 自然とのふれあい
- 公園や庭で自然を観察します。例えば、葉っぱや石の感触を触ったり、空の雲をじっくり眺めたり。
- リラックス効果があり、五感を使ったマインドフルネスにぴったりです。
5. マインドフルネス塗り絵
- 特別なテーマや自由なデザインの塗り絵を用意して、ゆっくりと塗ることに集中させます。これにより心が落ち着きます。
今度は子供すぎるかもしれないと思いながら、一応記載してみました。
効果的な学習時間配分
ポモドーロ・テクニックのような具体的な手法を紹介。
ポモドーロテクニックの基本的な手順
・タスクを決める:やりたい作業や学習内容を明確にします。
・25分間の作業:タイマーを25分にセットし、その間は1つのタスクに集中します。この時間を「1ポモドーロ」と呼びます
・短い休憩(5分)を取る:25分間の作業が終わったら、5分間休憩します。この間は席を立ったり、ストレッチをしたりしてリフレッシュします。
・4回繰り返したら長い休憩:4ポモドーロ(25分×4回)のサイクルが終わったら、15〜30分の長い休憩を取ります。この間に脳を十分に休ませます。
ポモドーロテクニックのメリット
- 集中力の向上:短時間で集中することで、作業効率が上がります。
- 達成感の提供:1つのポモドーロを完了するたびに小さな達成感を得られます。
- 燃え尽き防止:短い休憩を定期的に取ることで、疲労感を軽減できます。
- 時間管理の改善:タスクの見積もり力が向上し、作業時間をより効果的に使えます。
実践のコツ
- タイマーを活用:キッチンタイマーやスマホアプリを使うと便利です。
- 邪魔を排除:作業中は通知をオフにしたり、静かな環境を整えることが重要です。
- 柔軟性を持つ:25分にこだわらず、自分に合った時間設定にアレンジしてもOKです。
「効果的な学習時間分配」は記載内容が大人っぽい感じかなっと感じながらも、小さい子でも使える時間の分割方法だなっと思って、そのまま記載。
3. 子供のやる気を引き出すシンプルな方法
- 目標設定の楽しさ:小さな目標を達成するときの達成感を味わう工夫(シールやチェックリストを活用)。
- ポジティブなフィードバック:具体的に褒めるコツ(例:「頑張ったね!」ではなく、「ここまで工夫したのがすごいね!」)。
- 「ごほうび」設定のバランス:短期的なごほうびと長期目標の関連性をどう持たせるか。
4. 親ができる子供の学びの応援方法
- 効果的なコミュニケーション術:質問の仕方やアドバイスをするときの注意点(「なぜこれが難しいと思う?」などの開かれた質問)。
- 学習サポートの仕方:必要以上に手を出さない「見守りサポート」の重要性。
- 親子で一緒に学ぶ楽しさ:親自身が興味を持って一緒に学ぶことで、自然な学びの姿勢を見せる方法。
5. 集中を妨げる誘惑を減らす方法
- デジタルデトックスの導入:学習時間中のデバイス管理をどうするか。設定アプリやタイマーの活用例も。
- 運動とリフレッシュの取り入れ方:家の中でもできる軽い運動(ヨガやラジオ体操など)を提案。
子供の集中しやすい時間で区切って、休憩は体を動かしたり、リフレッシュできる方法で脳を休める。そしてまたお勉強スタート。年齢によってはやはり親がみてあげた方が良い年齢の子もいるでしょうが、主体性がみについてきた子供にはこういう方法があるよっというヒントを伝えてあげると、自分のものにできる子もいるでしょう。
すべてをやってみるのではなく、その子に合った方法を見付けるのが大事なので、親は口うるさく言うのではなく、見守ってあげたいですね。
臨時休校の話題かとおもいきや、子供の学習についての話ばかり。笑
大雪で大変な思いをするのは雪かきですよね。
今年は息子たちが大活躍してくれたので、とても楽をさせていただきました。
なにせ、わたくし風邪をひいておりました、いつもの半分も頑張れない状態。
息子たちよ、ありがとう!
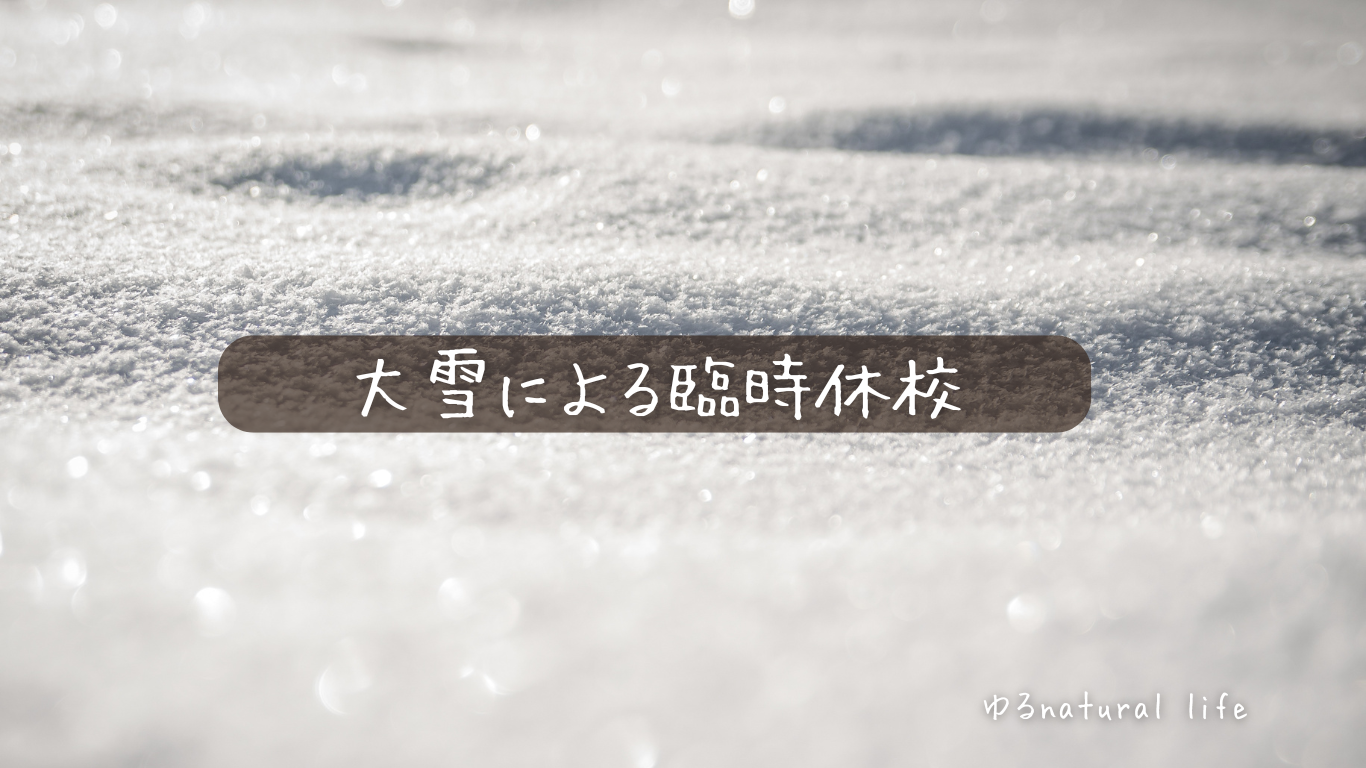
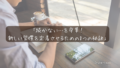

コメント