お正月休みも明け、皆さんはもう仕事始めされましたか?
お仕事が始まった方は、久々の長時間の勤務に疲れたと思います。
いつも働いているときは割と元気だったのに、正月明けはなんだか疲れがとれないな…と思う方いらっしゃいますよね。
お正月に暴飲暴食…とまではいきませんが、普段食べないような豪華なお食事をされていた方やいつもより1日の食べる量や回数が増えた方、長い休みに普段なかなか飲めないお酒をたくさん飲んだりと、お正月を満喫された方も多いのではないでしょうか?
それは普段よりも目一杯、胃腸をはじめとした消化器官が頑張って働いたということ。
ここで皆さんに質問です。
皆さんは1月7日に「七草粥」食べていますか?
なんでこの時期に七草粥を食べるの?って思う方も。
そもそも「七草粥」ってなぁに?という方もいるのではないでしょうか?
私自身はおかゆが好きで七草粥は食べる派ですが、家族はお粥かぁ…とあまり好んでは食べない感じがします🥹
しかし私は好きなのでやはり食卓に上がりました。笑
なぜ急に七草粥なのか
七草粥ってなんで1月7日に食べるの?私も毎年食べているものの、そもそも何の意味があるんだろう?年を重ねると、若いときに気にしなかったことがいろいろと気になってくる。今回はちょうど七草粥の謎を調べてみました。
1月7日は「七草粥」
1月7日に食べる七草粥は、正月のごちそうで疲れた胃腸を休める効果があるとも言われており、体に優しい行事食として親しまれています。
そして、七草粥を食べることで邪気を払って、一年の無病息災と五穀豊穣を祈る意味があるそうです。
1月7日は「人日(じんじつ)の節句」とも呼ばれ古くから日本で親しまれてきた行事だそうですが、そもそも「人日の節句」とは?
あまり聞き馴染みがないですよね。
日本の伝統食「七草粥」実は中国由来!?
人日の節句の由来ですが、中国の「七草の節句」に由来するそうです。中国では、陰暦の1月1日から7日まで、それぞれの日が特定の生物に関連づけられており、1月7日は「人の日」とされています。この日に、家族の無病息災や平和を祈るために特定の食べ物を食べる習慣がありました。
人日の節句については私も知らなかったので、AIさんとの会話で情報をいただきました✨
日本で七草粥が有名になったのは平安時代!
日本で広まったきっかけは、江戸戸時代には正月七日に将軍が七草粥を食べる祝儀が定着したそう。
ここから七草粥が庶民にも広まったとされていますが、元をたどれば七草粥は平安時代にまで遡るとされています。平安前期に猫好きとして知られる宇多天皇が初めて七種の若菜を入れた粥を神に供え、無病息災を祈念したことが始まりのようです。
やはり世の中に行事が定着するときは、偉い人や有名な方が一枚かんでいることがおおいようですね。
こうして1月7日に七種類の春の若菜を使った粥「七草粥」を食べる風習が根付いたそうです。
七草粥のメイン「春の若菜」
春の七草は栄養価が高く、冬の間に不足しがちなビタミンやミネラルを補う効果があるため回復食にはもってこいのレシピということです✨
七種類の春の若菜はこちら🔻
●セリ
●ナズナ
●ゴギョウ
●ハコベラ
●ホトケノザ
●スズナ
●スズシロ
七草に込められた意味
最後に七草には、それぞれが持つ特徴や形状に由来する意味が込められているのでそちらもご紹介。
セリ(芹): 芹には競り合うという意味があり、生命力や活力を象徴。
ナズナ(薺): ナズナは「撫でる草」とも呼ばれ、邪気を払い、健康を守るという意味があります。
ゴギョウ(御形): ゴギョウは「仏の座」に関連し、無病息災を祈る意味があります。
ハコベラ(繁縷): ハコベラは繁栄や繁茂を象徴し、家族の繁栄を願う意味があります。
ホトケノザ(仏の座): ホトケノザは仏像の台座に似た形から、安心と穏やかさを象徴。
スズナ(菘): スズナ(カブ)は根の形が鈴に似ていることから、子孫繁栄を願う意味があります。
スズシロ(蘿蔔): スズシロ(大根)はその白さから、清廉潔白を象徴し、健康と清らかさを意味します。
七草粥を食べることで、これらの意味が結びつき、一年の無病息災や健康を願う風習が根付いています。
みなさんも五穀豊穣、無病息災を願って七草粥を食べてみませんか😊

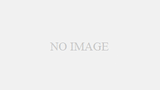

コメント